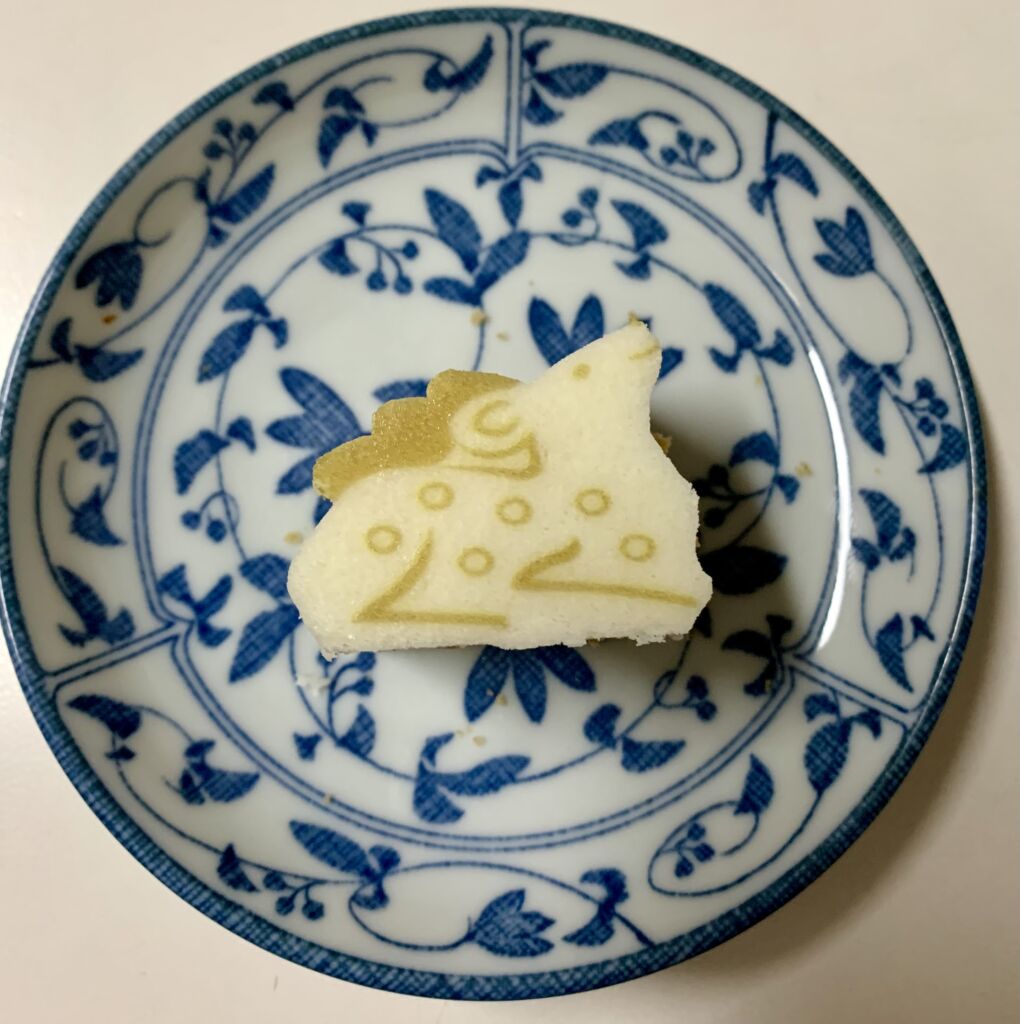五万石藤まつり 岡崎市
昨夜、五万石藤まつりに行きました。
藤の花が、絶賛ライトアップ中です☆
わが家から自転車で10分くらいで行ける岡崎公園
桜や藤など、お花見の時期には、近くてラッキーだなと、つくづく思います(笑)
去年も藤のライトアップを家族で見ましたが、今年は藤棚がさらに拡大されていました。
どんどん巨大化する計画でしょうか?
蔓を伸ばしているせいか、去年より花は小ぶり…
それでも、あたり一面が藤色に光って
映え映え☆
私が撮った写真とは思えないほど上出来(自画自賛、笑)

藤は「岡崎市の花」で、2022年には愛知県の天然記念物にも指定されたそうです。
ライトアップは5月5日(日祝)ころまでです☆(照明時間/18:00~21:00)
ぜひ見にいらしてください。
隙間時間にすること
最近、隙間時間にすることといえば、発表会の曲決めでした。
曲の雰囲気など、偏りの無いよう変化をつけ、楽しんでもらえる曲。
それでいて、何カ月もかけて練習するので、弾いていて上達できる曲。
なかなか纏まらず、時間がかかりましたが…
ようやく明けました☆
お土産
春休みのこと
息子から金沢のお土産を貰いました。(甘いものを控えているけど、やっぱり嬉しい。笑)
棒ほうじ茶ときな粉の和パフェサンドクッキー、緑茶にピッタリでしたよ♡
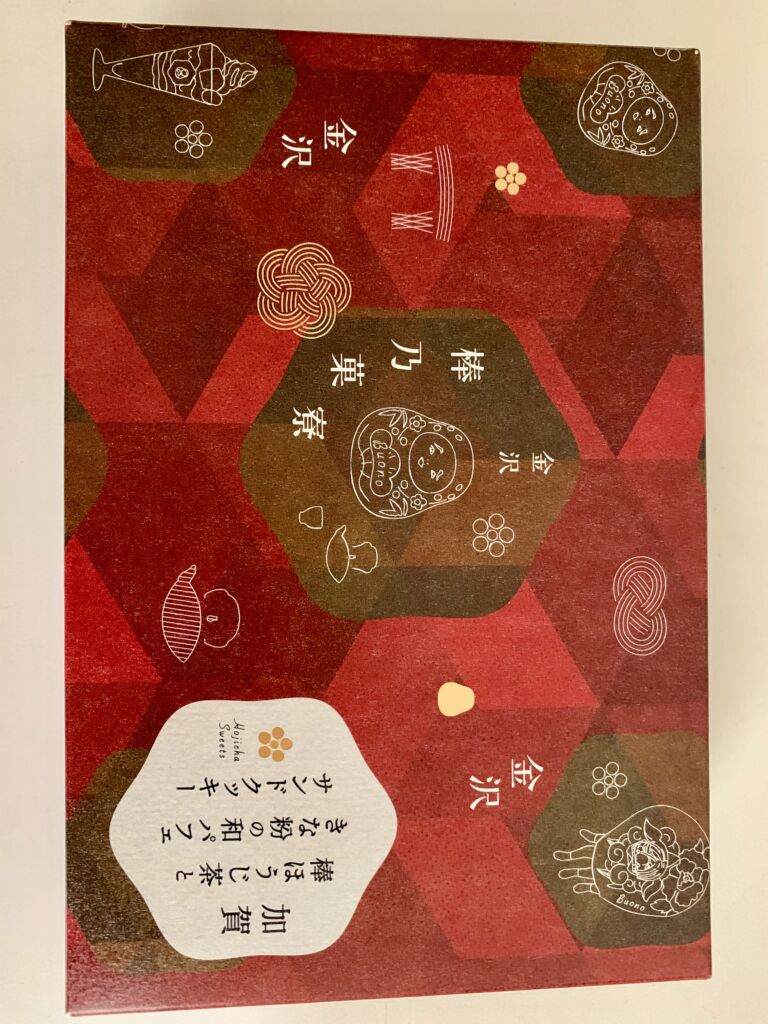

2024.4.29