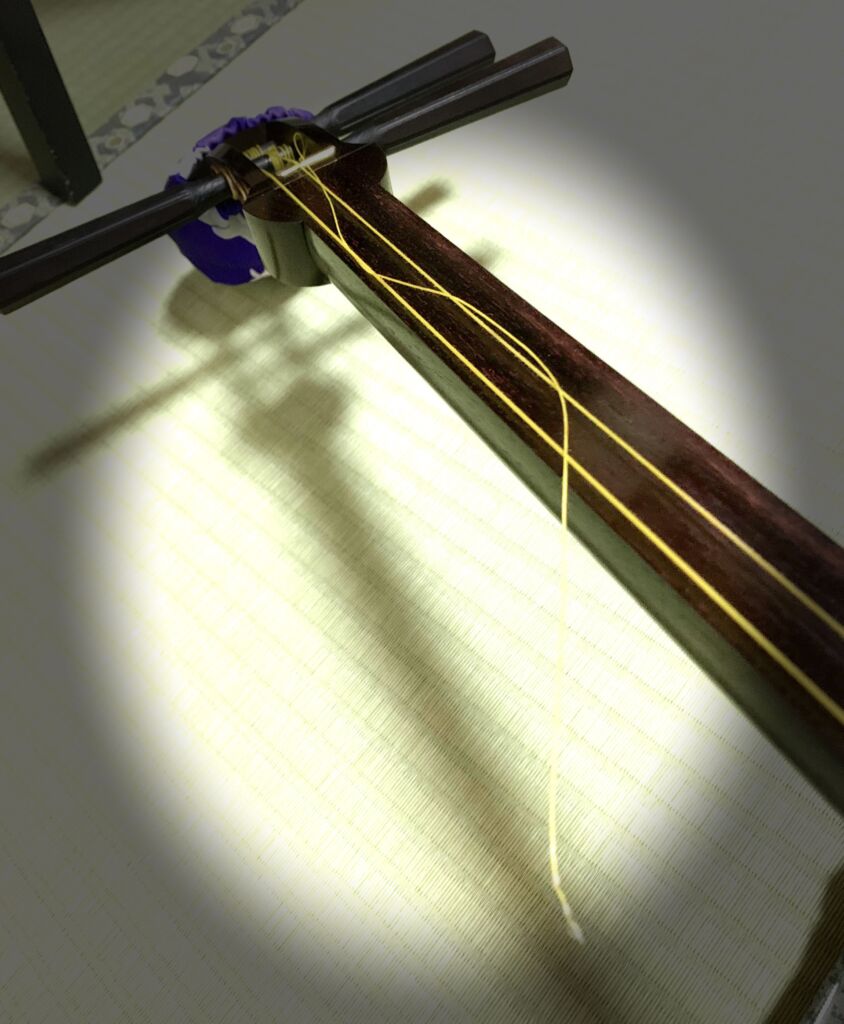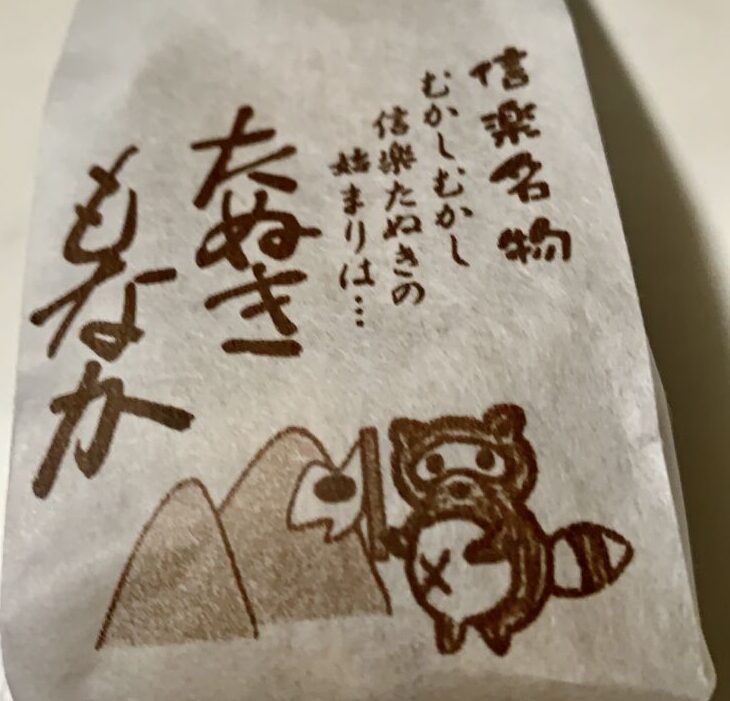今日は、あるものを断捨離しました☆
それは何かといいますと「ラインの公式アカウント」です。
思えば、あの入り口も 私には合っていませんでした。
全然活用していないので、思い切って「えいっ!」て感じです(笑)
管理は大して負担にはなりませんが、塵が積もって山とならないように。
めざせミニマリスト☆(到底難しいけど…)
今日は、少しだけ雑草を抜いて(まだまだ生えてる💦)
資源回収の用意(なんで こんなに溜まったの…新聞一つ辞めたい、笑)をしたら
着付けの練習、自信のお稽古、お箏を磨いて、お三味線のメンテもしようと思います。
予定通りいきますように◎
みなさん、良い一日を☆
ある日のレッスン風景
未分類
岡崎市お三味線教室|岡崎市お琴教室|思い切って断捨離
2023.9.5
10月におさらい会があります。
とっても楽しみ♪ な一方で、それぞれ曲がしっかり仕上がるが不安な気持ちもあります。
また、よく稽古して仕上げたつもりでも、本番は緊張して思い通り弾けないこともあります。その方が多いかな?
でも、しっかり稽古を積んだうえで、思うように弾けないのと、
曲が纏まらないまま本番をむかえるのとでは、わけが違います。
くり返しの稽古は、ある意味 地味で根気が入りますが
辛抱して取り組んだ分、必ず成長があると信じています。
🌸いつも自主練習ビデオを送ってきてくれるお弟子ちゃん、はじめと比べたら、見違えるほど強弾きになりました♪ お爪がしっかり絃をとらえています。小さな手でそのすべを習得できたことは大きな収穫です。
あとは、本番まで気持ちを切らさないで、くり返し稽古を続けること。そして、本番は、いつも通りの大きな声と大きな爪音で弾けば大丈夫☆ どんな発表になるか楽しみだな♪
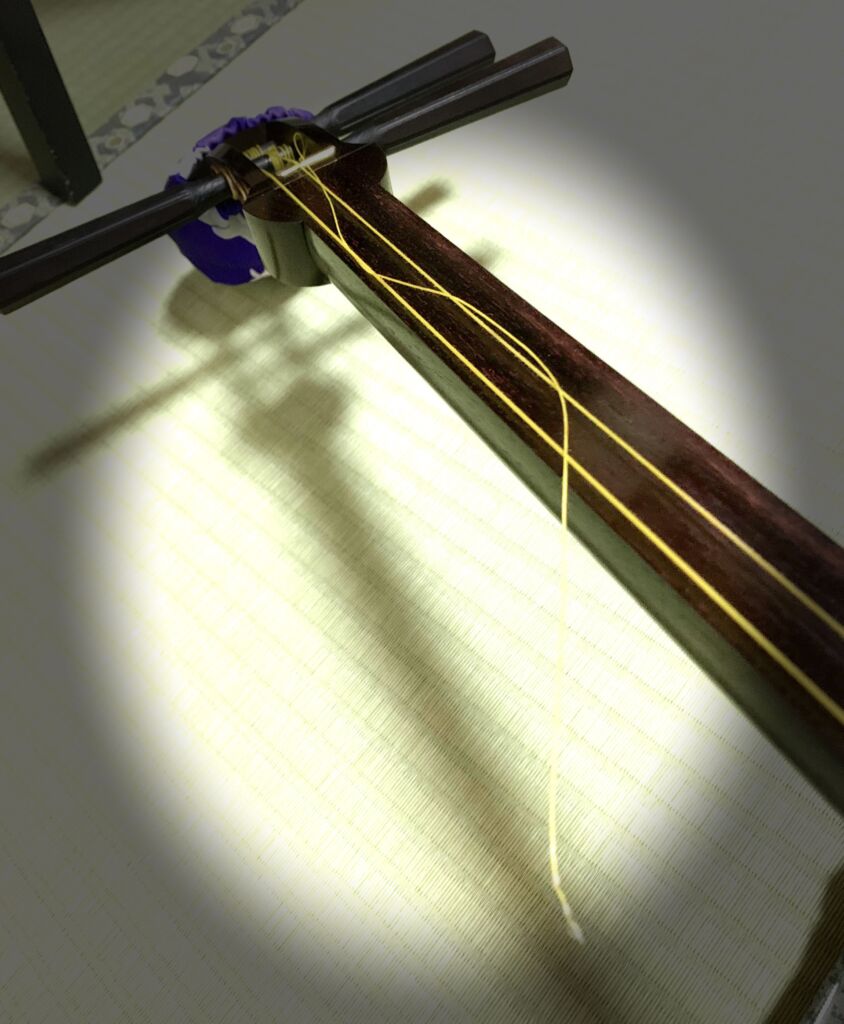
また切れましたっ💦 この現代曲は頻繁に切れる 切れない三味線の絹糸が欲しい(笑)
レッスン・琴・音色・工夫など
おさらい会にむけて|お稽古頑張ってます♪|岡崎市お三味線教室|岡崎市お琴教室
2023.9.3
先日、息子が信楽でお土産を買って来てくれました。
地元では有名な可愛いタヌキの最中なそうです♡
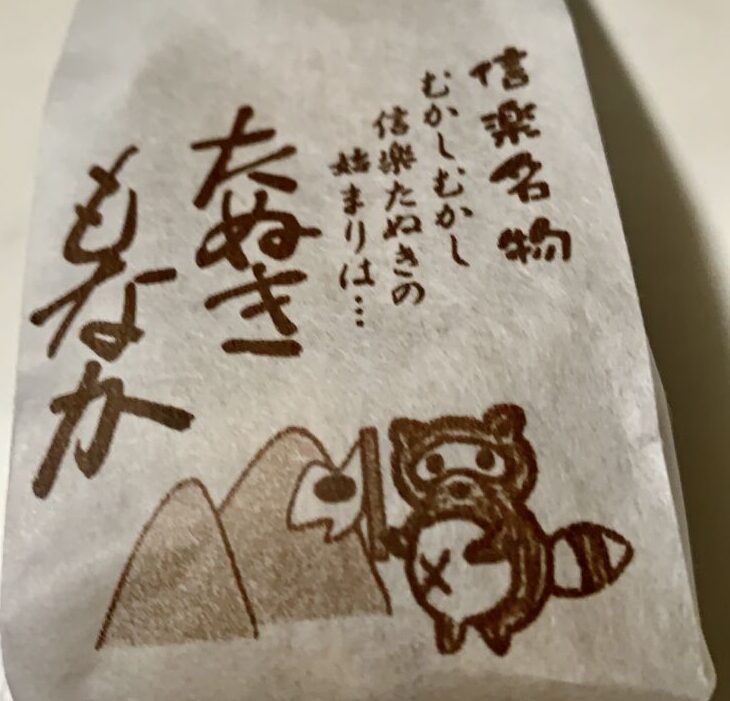

か、かわゆい?! 宇宙人? しばらく笑いました笑笑
可愛いかどうかは別として… 中にびっしりこしあんが詰まっていました☆
私は、信楽(しがらき)に行ったことがありません。以前、玄関に信楽焼の傘立てがあって、とても気に入っていたのですが、1年程で割れてしまいました。機会があったら、タヌキの置き物… じゃなくて!傘立てを買いに行きたいです!
未分類
タヌキか宇宙人か|信楽のお土産|岡崎市お三味線教室|岡崎市お琴教室
2023.8.22